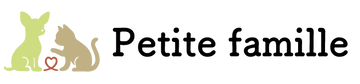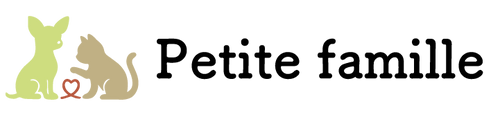ポメラニアンを飼う前に知っておきたいこと

チワワやトイプードル、ミニチュアダックスフンドに次ぐ人気を誇るポメラニアンですが、どの犬種にもいえるように飼う前にその特徴をしっかりと理解しておくべきです。
特徴を理解した上で飼うことができれば、犬も飼い主さんもハッピーに暮らしていけるでしょう。
そこで今回は、「ポメラニアンを飼う前に知っておきたいこと」について解説していきたいと思います。
ポメラニアンとは
それではまず、ポメラニアンがどのような犬種なのかを具体的に挙げていきましょう。
ポメラニアンはドイツ原産の小型犬で、スピッツとの品種改良を重ねて小型化させていった犬種となります。
体重は2.5㎏~5㎏程度ですが、元々が10kg前後ある犬種であるためかなり小型化された犬だといえます。
毛色はホワイトやブラック、ブラウン、レッド、オレンジ、クリーム、ブラックタンなど非常に多く、被毛は上毛と下毛があるダブルコートとなります。
被毛がふわふわなため、見た目も可愛く触り心地も最高です。
平均寿命は13歳~16歳程度ですが、運動や食事(ドッグフード)などに気を使えば18歳以上生きるケースもあります。
ポメラニアンを飼う前に知っておきたいこと
それでは、ここからは本題であるポメラニアンを飼う前に知っておきたいことをいくつか挙げていきましょう。
飼ってから驚くことがないように、ぜひすべてのポイントを覚えておきましょう。
①他の犬種と比べて抜け毛が多い
ポメラニアンはそのふわふわな見た目により、「抜け毛が多いのでは?」と思う方が多いですが、そのイメージ通り他の犬種と比べてもかなり抜け毛は多いです。
上毛と下毛の両方があるダブルコートであることが大きな要因だといえます。
そのため、こまめにブラッシングをしなければ、家中ポメラニアンの抜け毛だらけになってしまうでしょう。
ソファーなどでくつろぐ際にでも、ポメラニアンとコミュニケーションを取りながらブラッシングをすると良いでしょう。
②骨格的に怪我をしやすい
ポメラニアンは毛量が多くふわふわですが、サマーカットなどを行うとわかりますが体格はかなり細めです。
足も細く長いため、怪我をしやすい犬種であるともいえます。
特に前足を骨折してしまうケースが多いです。
骨折するケースとしては、「抱っこ中に落下して骨折」「飼い主さんが足を踏んで骨折」「足をドアに挟んで骨折しまう」「高い場所から飛び降りて骨折」などが挙げられます。
明らかに足が地面に着くのを嫌がる、触ると嫌がる、腫れているといった症状がある場合には骨折している可能性が高いため、早急に動物病院を受診すべきです。
自宅の段差を極力減らす、滑り止め対策をする、肥満に注意する、正しく抱っこするといった対策をしっかりと行うと良いでしょう。

③警戒心が強く吠えやすい犬種
ゴールデンレトリバーやパグ、シーズー、キャバリア、ペキニーズなどめったに吠えないような犬種もいますが、ポメラニアンはどちらかというと「吠えやすい犬種」に分類されます。
ミニチュアダックスのように声量が大きいわけではありませんが、声質が高いので吠え続けると嫌悪感を感じる人も多いはずです。
飼い主さんに要求している吠えなのか、警戒心からくる吠えなのか、寂しさによる吠えなのかなど、飼い主さんはポメラニアンの心理をしっかりと読み取ろうと心掛けるべきでしょう。
十分な運動やしつけ、社会性を身につけさせるといったことができれば、吠える機会も少なくなるはずです。
例えば、お留守番をさせた時には帰宅時すぐに思いきり抱きしめてあげたくなりますが、これは「吠えれば抱きしめてくれる」と思わせてしまう可能性があります。
嬉しさから吠えていたとしてもすぐに構わず、ある程度時間が経ち落ち着いてから声掛けし抱きしめてあげましょう。
④活発な性格だが散歩時間は短め
ポメラニアンはとても活発な性格の子が多く、実際にドッグランなどで放つとかなりのスピードで走り出します。
それゆえに、「散歩もたくさんさせた方が良いのでは」と思ってしまう飼い主さんも多いものです。
しかし、実際にはそれほど運動量自体は多くなく、1回15分程度の散歩を1日2回行う程度で十分なのです。
運動量に関してはそれほど注意しなくてもOKですが、飼い主さんと遊ぶことが大好きな犬種であるため、室内、室外問わずボールや縄、犬用おもちゃなどを使い一緒に遊ぶ時間を設けることは意識すべきでしょう。
まとめ今回は、「ポメラニアンを飼う前に知っておきたいこと」について解説してきました。
ポメラニアンはチワワやトイプードル、ミニチュアダックスに次ぐ人気を獲得していて、「飼ってみたいな」と思っている方も多いはずです。
・他の犬種と比べて抜け毛が多い
・骨格的に怪我をしやすい
・警戒心が強く吠えやすい犬種
・活発な性格だが散歩時間は短め
ポメラニアンには上記のような特徴があるため、実際に飼おうとするならばしっかりと理解しておくべきだといえるでしょう。